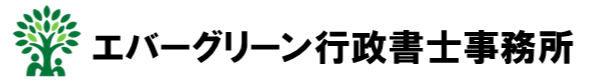遺言書の作成は、ご本人(被相続人)の財産相続に対する意思表示に法的効力を持たせて、後の相続手続において相続人間の揉め事や混乱を予防することができます。
【遺言書方式と作成の流れ】
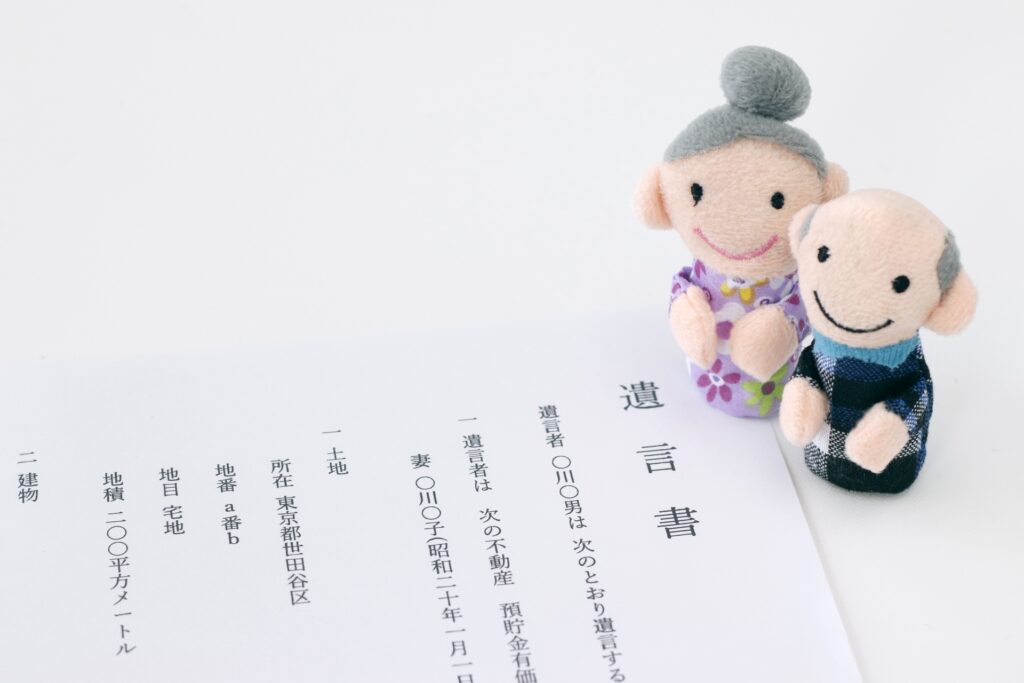
遺言書の方式には、主に自筆証書遺言、公正証書遺言があります。
【自筆証書遺言】
自筆証書遺言は手書きにより作成でき、最も簡易的な方式です。この方式は、遺言執行時に家庭裁判所での検認が必要となること、また遺言書の管理方法に不安が残るなど注意点もあります。この点に関し、2020年7月施行の「自筆証書遺言保管制度」を利用すれば、家庭裁判所の検認は不要、管理は法務局となり改善されます。。ただし、自筆のため内容等に不備があると法的有効性は保証されないリスクがあることに留意してください。
【公正証書遺言】
一方、公正証書遺言は、遺言者の意思を確認して証人2人の立会いのもと、公証人が遺言書を作成します。
公証人が事前に確認しているため、家庭裁判所の検認も不要で、保管も公証役場となり、法的にも確実で安全な方法です。
公文書であるため形式的証明力が働き、極めて強力な証拠力を有している点も複雑な相続関係に有効です。
◇公正証書遺言書の作成の流れ
公正証書遺言書の作成の流れは以下の通りです。
⑴ ご相談 : 財産相続におけるご本人の意思を実現させるための重要事項を明確にします。
⑵ 基礎調査 : 遺言の法的効力を確立させるために推定相続人・相続財産の調査をして事実確認をします。
⑶ 遺言書の原案作成: 公正役場で証人へ遺言書案を伝えるためのものです。
⑷ 証人の手配 : 公証人による遺言書作成では公証役場にて立会人2名が必要になります。
⑸ 公正証書遺言作成: 手順は、①遺言者の口授②公証人が筆記・読み聞かせする③遺言者・証人の署名押印となります。
【相続関係説明図の作成】

遺言書を作成するにあたり、または遺言書がない場合の相続手続(金融機関や法務局の手続等)で提出を求められることあるため、民法に従い推定相続人とその関係を明確にする目的で相続関係説明図を作成します。
戸籍(戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本)を取得して、それに基づき被相続人と相続人の続柄を家系図の形式で図式化します。
【遺産分割協議書の作成】

遺言書がない場合は、相続人により遺産分割の手続が必要で、それまでは共同相続人として共有の財産になります。
共同相続人により遺産分割の協議が調った分割方法・相続分等の決定した内容を文書にして、各相続人への所有権移転を証明するための書類が遺産分割協議書です。
【民事信託(家族信託)契約書等の作成】

民事信託契約とは判断能力がなくなる前に、本人の財産を主に親族に信託して管理・処分ができるようにしておく契約です。
作成した契約書は公正証書とすることで契約の説明力・信頼性が高まる、公証役場での保管で紛失や改ざんを防止できます。ただし、民事信託はあくまで財産管理を目的とする制度で、身上監護(生活・介護関係の管理)は後見制度を利用すること必要です。
お気軽にお問い合わせください。090-1835-7425受付時間 9:00-17:00 [土日・祝日除く ]
メールでのお問い合わせはこちら